こんにちは。「ガウ」です。
「老後2,000万円問題」
日本で生活している人は、耳にしたことがあるのではないでしょうか?
一時期、TVやネットニュースで毎日のように報道されていました。
簡単に言うと政府が

「国の年金じゃ足りないから、ちゃんとお金貯めておいてね」
と発言し、多く人が

無責任すぎる!
いきなりそんなこと言われても…
2,000万円なんて大金どうすればいいの!?
と困惑しました。
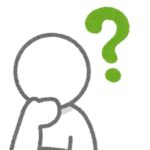
2,000万円も本当に必要なの?
と思う方もいるかもしれません。
しかし、
- 上がり続ける物価
- 遅れる年金受給開始
- 下がり続ける年金額
これらを考えると、公的年金だけで老後を暮らすのは難しいのではないでしょうか。
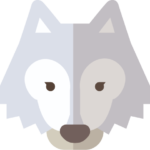
国に頼るだけでは、豊かな老後を過ごせない時代になったのかもしれない
僕自身は2021年時点で2,000万円以上の資産があり、FP3級というお金に関する資格もとったことで、老後資金の不安はあまりありません。
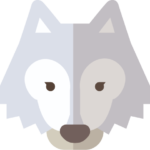
「ある程度のお金」「お金に関する知識」がないと不安は消えないよ
ということで、この記事では、老後不安を解消するために【老後2,000万円問題を解決する3つの方法】を紹介します。
具体的なプランは
- 2,000万円貯める
退職間近の50代、60代向け - 生活費を下げる
全世代共通 - 投資する
退職まで時間がある20代~40代向け
それぞれの方法と理由を詳しく説明していきます。

老後が不安だ…
というサラリーマンの参考になると嬉しいです。
老後2,000万円問題とは?
ことの発端は、金融庁が発表した「高齢社会における資産形成・管理」という報告書です。
その中に以下のような内容があります。
前述のとおり、夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦のみの無職の世帯では 毎月の不足額の平均は約5万円であり、まだ 20~30 年の人生があるとすれ ば、不足額の総額は単純計算で 1,300 万円~2,000 万円になる。
引用元:金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書 「高齢社会における資産形成・管理」
つまり
- 80歳以上まで生きると、年金だけでは足りない
- 足りない金額は最大で2000万円
ということ。
80歳というと、日本の平均寿命以下なので、多くの人がこの「老後2000万円問題」に該当します。
老後2000万円問題の前提条件
老後の収入(年金など):約21万円/月
老後の生活費:約26万円/月
という調査結果がもとになっています。
年金額:約21万円/月というのは、夫(会社員・公務員)、妻(専業主婦)の年金額に近い数値です。
つまり、老後2,000万円問題は夫(会社員・公務員)、妻(専業主婦)の世帯に当てはまります。
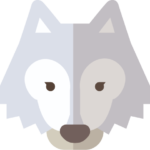
夫婦共働き世帯なら厚生年金だけでも暮らしていける
老後2000万円問題は起きない
逆に国民年金だけの世帯は2000万円じゃ足りない…
老後2,000万円問題を解決する3つの方法
- 2,000万円貯める
退職間近の50代、60代向け - 生活費を下げる
全世代共通 - 投資する
退職まで時間がある20代~40代向け
①2,000万円貯めてしまう
退職間近の50代、60代にオススメ
退職金+貯蓄のプラン
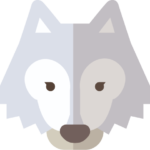
2,000万円足りないなら貯めてしまおう!
という考え方です。

2000万円なんて貯められないよ…
と思うかもしれませんが、公務員、会社員には「退職金」があります。
そのため、この方法は退職が近い50代、60代にオススメの方法となります。
逆に定年まで長い20代、30代にはオススメしません。
- 変化の激しい時代である
→ 今勤めている会社が倒産するかも - 下がり続ける給料
→もらえる退職金が少ない - 下がり続ける年金
→2,000万円では足りない
若い世代は②+③の戦略がオススメです。
退職金っていくら貰えるの?
学歴や会社の規模で異なるので幅が大きいですが、平均で約1000万円〜2500万円だそうです。
大抵は新卒から定年まで働けば、1,000万円以上は貰えるのではないでしょうか?
僕の会社の退職金
僕の勤めている会社で新卒(18歳)から定年まで働き、再雇用になった人に退職金聞いてみました。
退職金は約1500万円だったそうです。
ちなみに、会社の平均年収は300万円〜400万円、大企業の子会社です。
同じような境遇だと、在職中に500万円貯めれば解決します。
500万円なら、何とかなる気がしませんか?
世の中には、意外と簡単で効果の大きい節約方法がたくさんあります。

節約って何をしていいか全く分からない!
という方には、「本当の自由を手に入れる お金の大学」という本がオススメです。
節約に関することが分かりやすく、体型的に書かれています。
また、当ブログでも、節約方法、お金を貯めるコツを紹介しているので、よかったら他の記事も見ていってください。
退職金をローンに組み込んではいけない
「住宅ローンの返済」など、退職金の使い道がすでに決まっている人は、このプランを使うことができません。
そもそも論ですが、退職金を組み込んだローンの返済計画はオススメしません。
また、返済期間が60歳を超える住宅ローンもです。
退職金がいくら貰えるかも不明瞭ですし、せっかくの老後資金が台無しです。
- ローンは組まない
- 組むならできるだけ少額・短期間で
- 返済は60歳までに完了させる
どうしても退職金を使わなければならない場合は、②生活費を下げ、できる限り長く働く必要があるでしょう。
②生活費を下げる
全世代にオススメ
(年金)収入>生活費にする
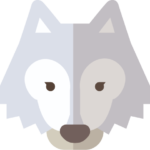
2000万円問題の原因は、毎月5万円の赤字
それなら、生活費を5万円下げて赤字にならないようにすればいい!
という考え方です。
赤字が解消すれば、そもそも2,000万円問題は発生しません。
貰える年金収入が月20万円なら、毎月20万円以下で生活する
→収入の範囲で生活する
これだけで老後問題は解決です。
年金が月20万円なのに、今は月30万円で暮らしている方は、退職後いきなり20万円で暮らすのは大変です。
退職が近いづいてきたら、少しづつ生活費を下げるようにしましょう。
また、これから給料が上がる可能性のある若い世代の方は、収入が増えても生活水準を上げないようにしましょう。
上がった生活水準を下げるのは、かなり大変です。
生活費を下げるには、先ほども紹介した「本当の自由を手に入れる お金の大学」が参考になります。
③投資する
20~40代にオススメ
投資の力を借りて「お金を増やす」
若い世代の方は、退職間近の世代と違い、大きなリスクを抱えています。
- 退職金が減る
- 年金額が減る
老後必要な金額が増えるリスク
老後2000万円では足りない可能性があります。
今の日本の情勢を考えると、確実に起きる未来でしょう。

2000万円でも大変なのに、どうすればいいの!?
老後まで時間のある若い世代は、投資の力を借りてお金を増やすのがオススメです。
シミュレーションしてみましょう。
毎月3万円、想定利回り5%の商品に30年投資すると、約2500万円になります。
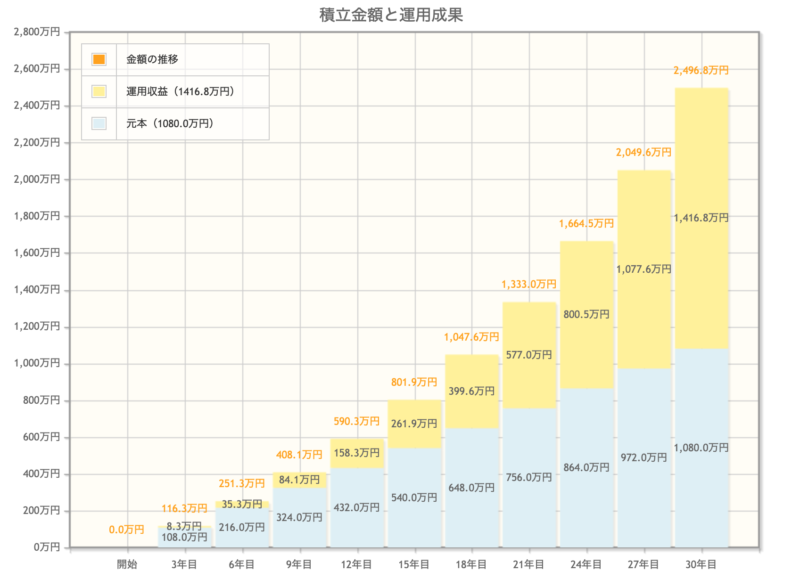
元金(青色)は約1100万円、利益(黄色)が約1400万円です。
退職金を合わせれば、3000万円以上用意できます。

投資って何だか怖いな…
と思う方もいるといるでしょう。
しかし「銘柄選び」を間違えず「長期投資」すれば、高確率で利益が出せます。
銘柄については、S&P500のような米国株インデックスへの投資です。
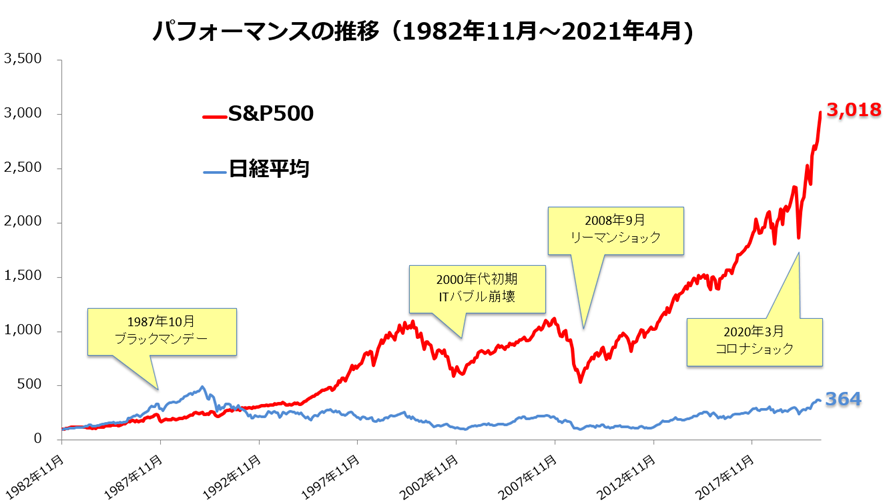
S&P500の平均リターンは約7%、先ほどの年率5%というのも現実可能な数値なのがわかります。
期間については、15年以上の長期間投資をする必要があります。
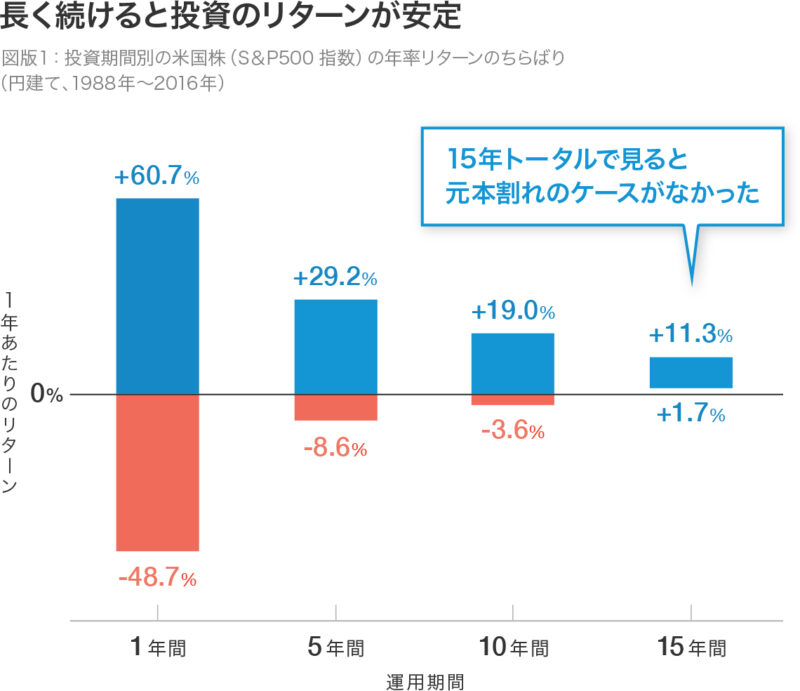
S&P500インデックスに投資した場合、15年以上投資するとプラスに収束しています。
「15年以上投資すると、損をする可能性はかなり低い」ということです。
なお、「長期間投資する必要がある」というのが、50代、60代にオススメしない理由です。
上のグラフを見てみると、10年以下だとマイナスになることも多く、1年間だと最大で「−48.7%」約半分になってしまうこともあります。
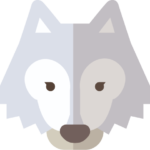
「いざ使おうとしたときに、お金がない!?」
ということもあるので、退職間近の人にはオススメしません
オススメの証券口座
投資をするには証券口座が必要です。
オススメの証券口座は以下の2つ。
どちらの証券口座も「口座開設は無料」「手数料が安く」「取扱商品が豊富」です。
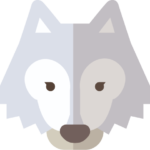
どっちにするかは完全に好みの問題
楽天市場で買い物をするなら楽天証券がオススメ
僕は両方持っています
積立NISA、iDeCoを活用しよう
投資で老後資金を作るなら、積立NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用しましょう。
投資で得た利益には、約20%の税金がかかります。
先ほどの例で出した利益約1400万円は、実際に引き出す際に約280万円税金で持っていかれます。
しかし、積立NISAやiDeCoを利用した場合、利益にかかる税金が非課税になります。
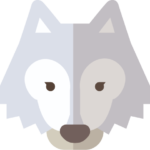
積立NISAは、証券口座を開設時に資料が送られてきます
案内に従って申し込もう!
iDeCoは少し複雑なので、まずは積立NISAがオススメ
「iDeCo公式サイト iDeCo(イデコ)をはじめるまでの5つのステップ」
まとめ 備えあれば憂いなし
- 2,000万円貯める
退職間近の50代、60代向け - 生活費を下げる
全世代共通 - 投資する
退職まで時間がある20代~40代向け
年金が全く貰えなくなることはないと思いますが、
- 年金の減額
- 平均寿命の増加
- 受給開始年齢の引き上げ
というのは高確率で起こり得るでしょう。
そうなった時に慌てないために、今から備えておくことが大切です。
(収入)年金はいくら貰えて(支出)生活にはいくら必要か?
この2つを把握して、自分たちに必要なお金を、必要な時期までに準備しましょう!

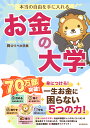


コメント